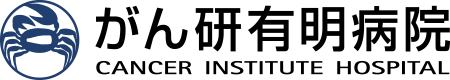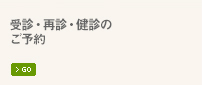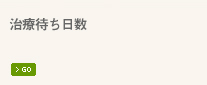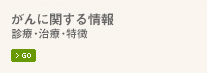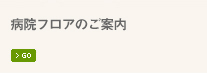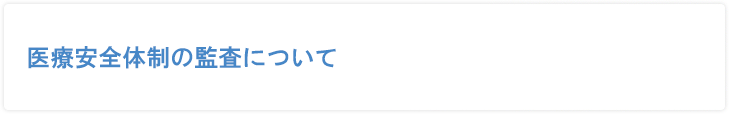
2024�N�x�@��P��
���v���c�@�l������L���a�@�@��È��S�č��ψ���@�č����ʊT�v
| ����� �F | 2024 �N 7 �� 25 ���i�j 11:55�`15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �ψ����F | ���� �\�� �i���É���w��w�������a�@���a�@�� ���҈��S���i������ �i��w���m)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ψ� �F |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q���� �F |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.�� ����
(1)�O��w�E�����̑Ή��y��(2)��Ö@�� 25 ���̋K��Ɋ�Â������������ʂɂ��Ĉ�È��S�Ǘ����������Ȃ��ꂽ�B
(1)2023 �N�x�� 2 ���È��S�č��ψ��w�E�����̑Ή���
�O��w�E�����@
�C���V�f���g�ɂ��āA��t�E�Ō�t�ȊO�̐E�킩��̃C���V�f���g���� 20���Ƃ���ڕW�B���Ɉ��������w�߂邱�ƁB
�i�Ή��j
�@���̊e�ψ���E��c�ɂāA�č��ł̎w�E�����Ƃ��ăt�B�[�h�o�b�N���s�����B2024 �N 1 ���ȍ~�͈�t�E�Ō�t�ȊO�̐E�킩��̃C���V�f���g���͑����X���ɂ���A�C���V�f���g����邱�Ƃ������Ƃ��č��t������ƕ]�����Ă���B���S�������������Ă������߂ɁA���������p�����A����̖{�ψ���ł����s�������B
�O��w�E�����A
����Ǘ��ɂ��āA�菇�̓O�ꂪ�K�v�ł���A�S���E�������炷��ۂ̎菇�̖��m���ƍs���̃��j�^�����O���d�v�ł���B
�i�Ή��j
2024 �N 5 ���ɍs���̏���ɑ���]�������{�����B�܂��A���i���S�Ǘ��ψ���s���@�����E���h�ł����j�^�����O���ڂɎ��グ�A�N�Q��̕]���y�ѕK�v�ɉ������t�B�[�h�o�b�N���s�����Ƃʼn��P�ɓw�߂Ă����B
�O��w�E�����B
IC �̂ЂȌ^�ɃR�X�g�i���ҕ��S�j�Ɋւ���L�ڂ��܂߂�Ɨǂ��B
�i�Ή��j
���� 900 ��ނ��镶���̊Ǘ����p���I�ɍs�����Ƃ͍���ł��邪�A����̌����ۑ�Ƃ������B
�O��w�E�����C
IC �̐R���̐��� 2 ���̈�t�ŒZ���Ԃɍs���Ă��邱�Ƃ���A�R����ɍ����o�Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁB
�i�Ή��j
���@�ł͐f�Ï��Ǘ��m�����O�ɓ��e���m�F���A���ȁE�O�Ȃ̊e�f�ÉȂ���I�o���ꂽ��t��Ō�t���m�F�Ɍg��邱�Ƃ���A���s�̐R���̐����p��������j�Ƃ����B
�O��w�E�����D
�R���ψ���̒��ɊO���ψ��i��Î҈ȊO�j�������邱�Ƃ���������B��Î҈ȊO�ł������ł��邩�Ƃ������_���K�v�ł���B
�i�Ή��j
���@�ł͐f�Ï��Ǘ��m�����Y�̖�����S�����ߌ���̑̐����p��������j�Ƃ����B
�O��w�E�����E
IC ��̊��҂̏n�����Ԋm�ۂ��ǂ̒��x�m�ۂ���Ă��邩������i�K�ɂȂ��Ă���B�n�����Ԃ̎��o�����ł���Ƃ悢�B
�i�Ή��j
���f������p���t���b�g��z�z���������d�˂�H�v�����Ă���B���@��� IC ���s�킴��Ȃ��ً}����v����P�[�X�ɂ��ẮA���@���\�ꂽ���_�� IC ��������t������Ŋm�F���ł���^�p������������j�Ƃ����B
�O��w�E�����F
�O���̏��u���̃^�C���A�E�g�ɂ��Ă͐����i�K�ł���B�N�P�I��Ís�ׂɂ�������S�m�F�ɂ��ẮA�O���E�a���ł����߂�����̂Ō������ꂽ���B
�i�Ή��j
�O���E�a�����킸�N�P�I��Ís�ׂɑ��Ă̓^�C���A�E�g�����Ă������j�ŁA�܂��͓��B�O�Ȃ̊O�����u�ł��� CNB�i�j�����j�ɑ��������A���j�^�����O�����{���Ă���B
�O��w�E�����G
�]�|�]���ɂ��āA���҂��ǂ̃G���A�ɂ��Ă��E�����Ń��X�N��F���ł���悤�ȍH�v���K�v�ł���B
�i�Ή��j
���҂��ǂ̃G���A�ɂ��Ă��]�|�]�����X�N���F���ł���H�v�ɂ��ẮA���肵������ł����̓I�ȑΉ����ł���ɂȂ��B
�O��w�E�����H
�O���̊e���Ɋۈ֎q���ݒu����Ă����B�]���h�~�̂��߁A�w������̂���֎q�ɂ���ȂǑ]�܂��B
�i�Ή��j
�]�|���X�N�̌����鉻��a�@�̉ۑ�Ƃ��Č������A�O���G���A�̊ۈ֎q��w������̂���֎q�ɑւ��Ă������j�Ƃ����B
�O��w�E�����I
PDCA �̓v������ 7�`8 ���̏d����u�����Ƃ��L�p�Ƃ���Ă���B�P�Ȃ�N���]���ƂȂ�Ȃ��悤�ȊǗ��̐��A�����E�w����ڎw���Ăق����B
�i�Ή��j
�w�E�������Q�l�ɊǗ��̐����\�z���ł���A��̓I�ȑΉ����ł���ɂȂ��B
�O��w�E�����J
���N�a�@�͏�ʎw�W�����A�e�����͂��̒����玩�����̖ڕW��I�����ĂP�N�Ԏ��g�ނƂ��� QI �̘A���̐���W�J����Ɨǂ��B
�i�Ή��j
QI �Ǘ��ɂ��Ă͓r�ɏA��������ł���A�܂��͎w�E������^���Ɏ~�߁A�a�@�̉ۑ�Ƃ��Č�������B�܂��A���N�x���p�t�H�[�}���X���|�[�g�̎w�W�Ǘ��ɂ��Ă͖ڕW�l�̐ݒ�����߂���j�Ƃ����B
(2)�֓��M�z�����ǁE�����s�ɂ���Ö@�� 25 ���̋K��Ɋ�Â������������ʂ̕�
2024 �N 7 �� 19 ���i���j�Ɏ��{�A�֓��M�z�����ǁE�����s�Ƃ��Ɂu�@�߂Ɉᔽ����悤�ȕs�K�ȕ����͖����A�T�˗ǍD�Ȍ��ʂł���v�Ƃ̕]�������B
2.�����
���@�̈�È��S�Ǘ��̐��Ǝ��g�ݏɂ��āA�u���ȕ]���\�v����Ɉψ����珕���E���s��ꂽ�B
- ��È��S�Ǘ��̐��̊m���i�K�o�i���X�̊m�ہj
- �a�@���̃��[�_�[�V�b�v�̉��ň��S�������W�J����Ă���B���҈��S����Ƃ��A����i��Â����s����ӎv�����m�ł������B
- ��È��S�Ǘ��ӔC�ҁE��È��S�Ǘ������𒆐S�ɃC���t�����ǂ���������Ă���A�������X�N�}�l�[�W���[�𑩂˂ēK�Ȋ���������Ă���B
- �������X�N�}�l�[�W���[�ɂ��ẮA�����ɂ���Ă͑�s�҂̐ݒ���������ꂽ���B
- ��È��S�Ǘ�����
- IA �����́A�K�ł���B���Ɉ�t�̕��������A�@���̏d��Č����L���b�`�A�b�v�����ŁA�K�v�\���Ȑ��ɓ��B���Ă���ƍl������B��t�E�Ō�t�ȊO�̐E�킩��̕�����N�x�� 12�����獡�N�x�� 19���֑����i�ڕW�l 20���ȏ�j���Ă���A����̎��g�݂Ɋ��҂���B
- �E��ʂ̕������Ɨǂ��B�܂��AIA �̖ڕW�l��݂��Ď��g�ނƗǂ��B�������m�ȖڕW�ݒ肪�Ȃ��̂ł���A�a�@�Ǘ��҂��c������K�v������C���V�f���g�� �X���ȏ��c���ł���Ɛ��肳��� IA �����Ƃ��āA�ȉ���ڈ��Ƃ����Ɨǂ��B
- �����ɂ����ĕa����×6.6 �ȏ�A����Ɉ�t����̕��ɂ����ĕa���� ×6.6×0.08 �ȏ�A���̓�̏����̓����B��
- �E��ɊW�Ȃ��A�����ɂ����ĕa����×8.2 �ȏ�
- ���҉e�����x�� 3a �ȏ�� IA ����
- �@�S���S���Ґ��A�A�d��ȃC���V�f���g���������}�����̐��̔��f��K�v�Ƃ��������A�B���ۂɎ��̒������K�v�ƂȂ��������A�C���̒����̌��ʁA���S��������Éߌ�ɂ��Ɣ��f���ꂽ���������o���ł���Ɨǂ��B
- �@���~�}�̐��ɂ����āAMET �v�������� 207 ��/�N�͗D��Ă���B
- ���ۓI�Ȉ�Î{�ݕ]���F�؋@�ւł��� JCI�iJoint Commission International�j�ł́Acode blue �i�X�^�b�g�R�[���j�� Rapid Response System�iMET �v���j�� Early Warning Score�i�����x���X�R�A�j�� 3 �̑̐��������Ƃ𐄏����Ă���B�������I�ϓ_�� Early Warning Score
�i�����x���X�R�A�j�̓��������������Ɨǂ��B - QI ����i��Õi�����P���j�ŁA���݉@���œ����Ă���w�W���ꌳ�Ǘ��ł���Ɨǂ��B�a�@���������N�ł��o���ڕW�̒�����A�e����̔N�x�ڕW���I�������A������K�o�i���X�̈꒼�����̐����]�܂����B
- ���҂̌����ۏ�̎��g��
- �ЂȌ^�ɉ����� IC �����̍쐬�Ǝg�p�p�x�̊Ǘ��ɂ��āAIC �ψ����̉��A���ݖ� 900 ��ނ��� IC �����̌������v�悪�T�˒�܂�A���N�x���ɃR���e���c�̕s��������_�����Ă����\��ƂȂ��Ă���BIC �̈ꌳ�Ǘ����K�ɉғ����n�߂Ă���B
- ����x�V�K��ËZ�p�������̃v���Z�X
- ����x�V�K��ËZ�p�]���ψ���Ɩ����F�V�K��ËZ�p���]���ψ���̑o���̕]���Ƀo�����������悤��ÃN�I���e�B�}�l�W�����g�Z���^�[�^�c�ψ���ŕ]����������L����Ă���A�K�ƌ�����B
- ���̖h�~��̎���
- �m���Ȋ��Ҋm�F��IPSG�i���ۊ��҈��S�ڕW�FInternational Patient Safety Goal)�̑� 1 ���ڂɊY������B���ۊ�ł́A���ґ�����ʎq�M�����A��Î҂̎茳�ɂ���ʎq�Ɠˍ�����Ȃ�����͎��̍s�ׂɈڂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���B�a�@�Ƃ��āA���ۊ�Ɋ�Â����@�Ŏ菇�����������Ƃ��������ꂽ���B
- �����w���`�B�� IPSG�i���ۊ��҈��S�ڕW)�̑� 2 ���ڂɊ܂܂��B�u�����w���͌������Ȃ��E�Ȃ��v����{�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͗ǂ����A�u�Ō암�v�݂̂ł͂Ȃ��A�u�a�@�S�́v�Ń��[��������K�v������B
- �}�[�L���O�� IPSG�i���ۊ��҈��S�ڕW)�̑� 4 ���ڂɊY��������S�s���ł���B�}�[�L���O�Ɋւ���菇��[�������ۊ�ɑ����Č������Ɨǂ��B
- ���҂̓]�|�E�]���̗\�h�� IPSG�i���ۊ��҈��S�ڕW)�̑� 6 ���ڂɊY������B�]�|�̃��X�N�����銳�҂�N�����Ă��킩��悤�ɂ��邽�߃��X�g�o���h�ɕW���i�F�j��t����Ȃǂ̕��@���̗p���邱�Ƃ��]�܂��B�O�����҂͖ڎ��Ŕ��f������Ȃ����A�]�|���X�N�̍������҂����ʂ��邽�߂̃��[�������������Ɨǂ��B
- B �^�̉��Ǘ��̐��A��ʏo���Ǘ��̐��͗D�ꂽ���g�݂Ƃ�����B
- ��܊Ǘ��̎���
- �^�`�Ɖ�ɂ����āA��t�̔�Ή������𐔒l�����Đf�Éȕʂɉ�����s�����Ƃ͏d�v�Ȃ��Ƃƍl����B����A�����Ɨǂ��B
- ��È��S�Ǘ�����ƘA�g���Ď��g�C���V�f���g�����ɂ��āA����A���i���S�Ǘ��ӔC�҂�������Ɨǂ��B
- �^�`�Ɖ�ɂ����āA��t�̔�Ή������𐔒l�����Đf�Éȕʂɉ�����s�����Ƃ͏d�v�Ȃ��Ƃƍl����B����A�����Ɨǂ��B
- ��Ë@��Ǘ��̎���
- ��Ë@��̍w���E�X�V�ɂ��āA�T�˓K�ɊǗ�����Ă���B
- ���ۊ�ł͂��ׂẲ@���̈�Ë@��ƈ�Íޗ����ꌳ�Ǘ��ł��Ă��邩������Ă���A�������I�ȉۑ�Ƃ��Č��������Ɨǂ��B
- ��È��S�Ǘ�����ƘA�g���Ď��g�C���V�f���g�����ɂ��āA����A��Ë@����S�Ǘ��ӔC�҂�������Ɨǂ��B
- ��Õ��ː��̊Ǘ��̎���
- ���U������ʁA�f�ÉȁE�������ڕʂ̑�������ʂȂǂ̔c���������Ɨǂ��B������ʂ̑����J�e�S���[�肵�ĉ�����Ă������Ƃ�����̉ۑ�ƍl����B
3.�č����ʁi���]�j
- ����@�\�a�@�ɑ��āA��Ö@�㋁�߂����{�I�Ȉ�È��S�̃K�o�i���X�̐��⏳�F�v�������Ă��邱�Ƃ��m�F�����B
- �a�@���̓K�ȃ��[�_�[�V�b�v�̉��A���҈��S��̑̐��A�K�o�i���X�����邽�߂̈ψ����e WG �̐ݒu�ȂǁA���҈��S�̂��߂̃C���t������������Ă���A�e���S�ӔC�҂��K�ɑΉ���}���Ă���B
- ����u�i5�j���̖h�~��̎��ہv���ɂ����āA�������d�v�ȉۑ肪�w�E���ꂽ�B�i5 �ŎQ�Ɓj
- ����̊č��́A�č��p���i���ȕ]���j����ɂ���`���ŏ��߂Ď��{�������A�����܂Ńy�[�p�[��p�����O�`�ɑ���]���ł���B�č��ő�Ȃ��Ƃ́A��w���̈Ӑ}���A����łǂꂭ�炢���H����Ă��邩���O���̖ڂŎ��ۂɌ����A���o�����ۑ����w���Ƀt�B�[�h�o�b�N���邱�Ƃł���B����̊č��Ŋm�F�������B
2024�N�x�@��Q��
������L���a�@�@2024�N�x�@��2���È��S�č��ψ���@�č����ʊT�v
| ����� �F | 2025�N2��21���i���j13�F00�`16�F00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �ψ����F | �����@�\��@�i��t�F���É���w��w�������a�@�@���҈��S���i���@�����j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ψ� �F |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q���� �F |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.����
�����Ɋ�Â����@�̈�È��S�Ǘ��̐�����сA�O��̎w�E�����ɑ�����g�݂ɂ��Ċe���������s�����B
- ��È��S�Ǘ��̐��ɂ��āF
- �C���V�f���g�E�A�N�V�f���g���|�[�g�̕ɂ���
�O���t��p���ĒB�O��A�����̂��������̖ڕW�l���A�S�ď��錋�ʂł������������ꂽ�B - ���݃��E���h���{��
�Ջ���ȑ�w�a�@�ƍs�������݃��E���h�ɂ��ĕB�����̂��������X�g�o���h�������j�ɂ��Ẳ��P���ꂽ�B - �L�Q���ے����ψ���E���ጟ�����ψ���J��
�J�Â��ꂽ����̒�����5����s�b�N�A�b�v���A���ꂼ��T�v�A�v���A���P��ɂ��ĕ��ꂽ�B
- �C���V�f���g�E�A�N�V�f���g���|�[�g�̕ɂ���
- �O��̎w�E�����ɑ�����g�݂ɂ��āF
- �O��w�E�����@
�����p���̗l���ꂵ�A�UR�����ɓ_�����Ȃ���L�ڂ��A�ǂݏグ��菇�ɂ��������ǂ��i2023�N�x�j
�Ō암�݂̂ł͂Ȃ��u�a�@�S�́v�Ń��[��������K�v������i2024�N�x�j
�i�Ή��j
2023�N�x�̎w�E�����������Č������A�����w�������̋L�ړ��e�̌��������s���A�g�p�����̒NjL�A�S�E�킪�g�p�ł���悤�u�Ō�t�v�̕\�L���u��M�Җ��v�ɕύX�B�����6�q�ɉ����č��ڗ��Ă��l���ɕύX�����B�����ēd�q�J���e�̃e���v���[�g�������ɏ��������e�ɕύX���A�S�E�����g�p�ł���悤�i�r�Q�[�V�����}�b�v�Ɏ��ڗ\��ł��� - �O��w�E�����A
���҂̓]�|�]���\�h�ɂ��āA�O�����҂͖ڎ��Ŕ��f������Ȃ����A�]�|���X�N�̍������҂����ʂ��邽�߂̃��[�������������Ɨǂ�
�i�Ή��j
�O���G���A�œ]�|���X�N�̍������҂�E�����o�m�ł���d�g�݂̋�̍���������A�Ăяo����M�@�t�H���_�[�̃X�g���b�v�R�𗘗p���ă��X�N�̍������҂����ʂ���^�p���������ł���B�����X�N���҂͉��F�̃X�g���b�v�Ƃ��A4�����^�p���J�n����\��ł��� - �O��w�E�����B
��p���ʃ}�[�L���O�ɂ��āA�菇��[�������ۊ�ɉ����Č������Ɨǂ��B�}�[�L���O�Ώۊ��҂ɂ��ẮA���E�̂Ȃ����ʂł����Ă��㕠���A�������̈Ⴂ�ɂ��Ă��}�[�L���O���鎖�𐄏�����B�܂��A�}�[�L���O�Ɏg�p����y���ɂ��Ă͔畆�y�����g�p���P��g�p���]�܂���
�i�Ή��j
���ۊ�ł���u���ۊ��҈��S�ڕW4�v����сu�v�g�n�K�C�h���C��2009�v�ɖ��L����Ă����Ɠ��@�̌��݂̉^�p���ƍ��������ʁA���ۊ�ɏ��������^�p�ł���Ɣ��f�����B
�}�[�L���O�Ώۊ��҂ɂ��Ă͓��@�̓��������ӂ݁A���c�̌��ʁA�]�O�ǂ��荶�E�A�����̍\����x��������ꍇ�Ƀ}�[�L���O���s���^�p�Ƃ����B�畆�y���ɂ��Ă͋��c�̌��ʁA�}�[�L���O��p�̃y�����e�a���ɔz�u���鎖�Ƃ����B - �O��w�E�����C
�^�`�Ɖ�ɂ����āA��t�̔�Ή������𐔒l�����Đf�Éȕʂɉ�����s�����͏d�v�ł���A������ꂽ���B
�i�Ή��j
2024�N�x�㔼���̋^�`�Ɖ�ɂ�鏈���ύX�����Ƃo�a�o�l�Ή�����B�����ύX���ꂽ������68���ł���A���̂�����t�ɂ��o�a�o�l�ɂ��C����24���ł������B�����āA�f�ÉȖ��̋^�`�Ɖ������ѕύX�����������B
2.�č����ʁi���]�j
����@�\�a�@�̗l�X�ȗv���ɂ��Ă͌p�����ēK�ȑΉ����Ȃ���Ă����B���ɁA�s���ɂ��Ă͔��Ɋ���������Ă���A��t�A�Ō�t�ȊO�̕��܂ߓK�Ȍ������ێ��ł��Ă���B�܂��A�d��Ȗ��̃g���A�[�W����A���A���́A�Ĕ��h�~��̗��Ă��s���A�K�ȍĔ��h�~������Ă��鎖���m�F�ł����B����ɉ��P���]�܂�鎖���Ƃ��āA�ȉ��ɂ��Ďw�E����B
- �d��Ȏ��̂ɑ���Ĕ��h�~��ɂ��āA�@���ł����ɒ蒅���Ă��邩���m�F���A��̓I�Ɏ����i�K�ɂ���ƍl����B�Ⴆ�A�l�������Ƃɉ@�����E���h�ɂ����Ē蒅�x���m�F����ȂǁA��旧�Ă����Ĕ��h�~��̒蒅�x���v��t�H���[�A�b�v�̐��̐������]�܂����B
- �@�������̍ۂɕa�@�S�̖̂ڕW�ɂ��Č���E���֊m�F�����Ƃ���A�����̐E�����w���Ҍ�F�h�~�x�ł��邱�Ƃ�F�����Ă������A���������␄�ڂȂǂɂ��Đ�����p���Đ����ł���E���͂��Ȃ������B�a�@�S�̂̕��j��F��������ŁA�\���I�Ɏ~�ߍs���ł���E���������鎖���]�܂����B
- ��È��S�}�j���A���̌g�s�ɂ��āA���m�O�ꂳ�ꂽ���B
- �ߋ��ɔ��������d�厖�̂ɂ��āA�E���̔F�m�x���グ��Ɨǂ��B
- �^�C���A�E�g�A�T�C���C�����̃`�F�b�N���X�g�̍쐬�A�ˍ����@�̐������s�������]�܂����B
- �����ɏ����Ȃ��ꍇ�̌����w���̊m�F���@�ɂ��Ď菇�������s����Ɨǂ��B
- �}�[�L���O�ɂ��āA�S��ΏۂƂ��邱�Ƃ𐄏�����B�S���ΏۂƂ��Ȃ��ꍇ�A��p���ɉ^��銳�҂̒��Ƀ}�[�L���O����Ă��Ȃ����҂��܂܂�Ă���A���̎��������炷���X�N�ɂ��ĔF�����������ŁA������p�����đΉ����������ꂽ���B
- �@�������̍ۂɃ}�[�L���O�̕��@�ɂ��Ď��₵���Ƃ���A�p�n�ɉ����ă}�[�L���O����A�Ɖ���A�ۈ�ł���Ɩ��m�ɉ���Ȃ���������������ׁA�m�F���ꂽ���B
- �������|�[�g�̖��ǁE���ǂ̊Ǘ��A����ёΉ��E���Ή��̊Ǘ��Ɋւ��āA�d�v�ȉۑ�Ƃ��č���̎��g�݂��������ꂽ���B
- ���[������ɂ����Č����Ɨ�O���敪���Ė��L���鎖�����邪�A��O���߂�ꍇ�͂ł�������̓I�ɖ�������Ɨǂ��B
�R.����̈�È��S�O���č��ψ���Ɍ�����
- ��ܕ��̋^�`�Ɖ�ɑΉ����Ȃ������P�[�X�ւ̃t�H���[�A�b�v�ɂ��āA����ȍ~�A�����������ꂽ���B
- �@���������s���ۂɂ́A��t�ɒ��ڃq�A�����O���s�����߁A�e������ɕK����t�𗧂���킹�邱�Ƃ���]����B
�ȏ�