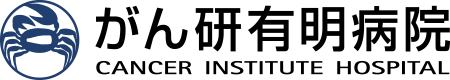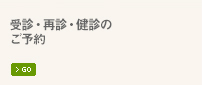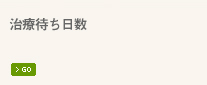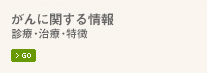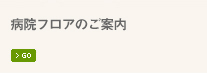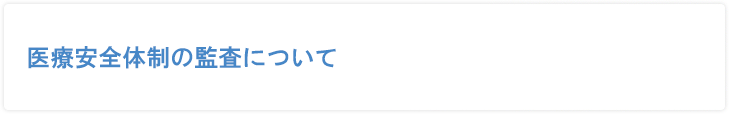
2025�N�x�@��P��
���v���c�@�l������L���a�@�@��È��S�č��ψ���@�č����ʊT�v
| ����� �F | 2025�N7��24���i�j13�F00�`16�F00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �ψ����F | �����@�\��@�i��t�F���É���w��w�������a�@�@���҈��S���i���@�����j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ψ� �F |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q���� �F |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.����
�����Ɋ�Â����@�̈�È��S�Ǘ��̐�����сA�O��̎w�E�����ɑ�����g�݂ɂ��Ċe���������s�����B
�@�@
(1) ��È��S�Ǘ��̐��ɂ��āF
�@�C���V�f���g�E�A�N�V�f���g���|�[�g�̕ɂ���
- �O���t��p���ĒB�O��A�����̂��������̖ڕW�l��S�ď��錋�ʂł������������ꂽ�B
- 2024�N�x���A�����Ɋւ���C���V�f���g���C���V�f���g�V�X�e����p�����̑ΏۂƂ��A�]���͎��}�̂��g�p���Ă�����Ë@��Ɋւ���C���V�f���g���C���V�f���g�Ǘ��V�X�e�����g�p����̕��@�ɕύX�������Ƃ�IA�̑�����2023�N�x�Ɣ�r���Ė�1,000�����������B
- �E��ʕɂ��ẮA��t�E�Ō�t�ȊO�̐E�킩��̕�������20���߂��܂ŏ㏸���Ă���A�K�ȕ����E�킩���o����Ă��錋�ʂł������B
- �w��Ís�ׂ����{�����ʂł̊��Ҍ�F���[���ɂ���x��2025�N�x�̖ڕW�Ƃ��A�������Ɏ��g�ݖڕW��ݒ肵�A�Ǘ��������Ȃ��Ă���B�܂��A���Ҋm�F�̕��@���t���l�[���݂̂̈ꎯ�ʎq����A�t���l�[���Ɛ��N�����܂���ID�ԍ��Ȃǂ�p�����ʎq�ɕύX����\��ł���A���N�x�̖{�ғ��Ɍ��������������J�n���Ă���B
�A�L�Q���ے����ψ���E���ጟ�����ψ���J��
�J�Â��ꂽ3��ɂ��āA���ꂼ��T�v�A�v���A���P��ɂ��ĕ��ꂽ�B
�B�����ǁ^�����s������������
�V��17���Ɏ��{���ꂽ������/�����s�̗��������ɂ��āA���ɑ傫�Ȏw�E�����͖����I���������Ƃ����ꂽ�B
(2) �O��̎w�E�����ɑ�����g�ݓ��ɂ��āF
�@�����w���`�B�ɂ���
�O��w�E����
- �����p���̗l�������ꂳ��Ă��Ȃ��B�����p���̗l���ꂵ�A6R�����ɓ_�����Ȃ���L�ڂ��ǂݏグ��菇�ɂ��������ǂ��i2023�N�x�j
- �u�Ō암�v�݂̂ł͂Ȃ��A�u�a�@�S�́v�Ń��[��������K�v������i2024�N�x�j
�i�Ή��j
�d�q�J���e�������ꍇ�̌����w�������ꂵ�A��t���ً}���ȂǓd�q�J���e�̃I�[�_�[���͂��s�\�ȏꍇ�̂ݎg�p�\�ł��邱�ƂL�B�Ō�t�ȊO���g�p�\�Ƃ��A6R�����ɓ_�����Ȃ���L�ڂł���悤���ڗ��Ă��l���ɕύX���A�L�ڌ�̃��[�h�o�b�N�ɂ��Ă��`�F�b�N���ڂ�NjL�����B�����āA�d�q�J���e������ꍇ�̌����w���e���v���[�g�������w�������ɏ��������e�ō쐬���A�^�p���J�n�����B�^�p�J�n��A�����w���e���v���[�g�̎g�p���������ʁA���������w���͋֎~�ł���ɂ�������炸�A�����w���e���v���[�g�����p����Ă���A���[�h�o�b�N�������s���Ă��Ȃ��ł������B�܂��A���M�ґ��������w����`������ɓd�q�J���e�Ɏw�������͂���Ă��Ȃ����U�����ꂽ�ׁA�����w���e���v���[�g�̎g�p�ɂ��ĉ^�p�̐�����\�肵�Ă���B
�i����w�E�����j
���[�h�o�b�N�̌�Ɂu���F��v�Ƃ������ڂ�lj������Ɨǂ��iClosed-loop Communication�j�B�܂��A�o���I�Ƀ��[�h�o�b�N���⏳�F���A�ǂݕԂ������߂����Ȃǂ𐔒l�������m���鎖���]�܂����B
�A�����h�~�ɂ���
���@���̊��҂��{������̂ǂɋl�܂点�������A�X�^�b�g�R�[����v����������̔������A�H���ɂ�钂����h�~���邽�߂̑̐�������ړI�Œ���WG�����A�������X�N�̒ጸ�Ǝ��̔������̔�Q�̍ŏ����Ɍ������̐������������Ȃ����B
�Ō�t�����@��24���Ԉȓ��܂��͐�H���Ԃ�72���Ԉȏ�ł��������҂̃��X�N�]���������Ȃ��A�����X�N���҂ɂ������Ă͑��E��őΉ�����^�p�Ƃ��A2025�N8������^�p���J�n����\��ł���B
�i����w�E�����j
���҂̌��o���̕ω��ɑΉ��ł���d�g�݂Â��肪�K�v�ł���B���{�݂̎��g�݂��Q�l�ɂ����Ɨǂ��B
�B�^�`�Ɖ�ɂ���
�O��w�E����
��ܕ��̋^�`�Ɖ�ɑΉ����Ȃ������P�[�X�ւ̃t�H���[�A�b�v�ɂ��āA����ȍ~�A�����������ꂽ���B
�i�Ή��j
2024�N�x�������̋^�`�Ɖ��̏����ύX���������ꂽ�B�w�ύX����x��69���A�w�ύX�Ȃ��x��31���ł������B����ɁA�f�Éȕʂ̋^�`�Ɖ���ƕύX�����A�^�`�Ɖ�ޕʌ����Ȃǂ̏W�v���ʂ����ꂽ�B���̑��A�^�`�Ɖ��ɕύX����Ȃ������P�[�X�̃t�H���[�A�b�v�ɂ��āA�֊���ɑ��鎖��3����s�b�N�A�b�v���ĕ����B
�i����w�E�����j
�^�`�Ɖ��̏����ύX���̓v���Z�X�w�W�ł���A�v���Z�X�Ǘ��̌��ʁA�s�K�Ȗ�g�p�ɂ��L�Q���ۂ̔����������Ɍ��点�邩�A���S����ƘA�g���֘A����C���V�f���g���̑��������j�^�����O���鎖���]�܂����B
�@���ҎQ��ɂ���
���҂ɑ���T�[�r�X�̌��ゾ���łȂ��A�d�g�݂Ƃ��č��ȏ�Ɋ��ҁi���ґS���j����Î҂Ƌ������Ď��̍�����Â���������̐��̍\�z��ړI��2025�N5���Ɋ��ҎQ���Ð��i�ψ�����������B�܂��A���Y�ψ���̎w�j��A���łɎn�܂��Ă�����g�݁A����̊����\��Ȃǂ��Љ���B
�i����w�E�����j
PX�ipatient experience�j�̑���Ɏ��g�܂��Ɨǂ��B���Y�ψ���Ō������ꂽ���B
�C���t�H�[���h�R���Z���g�ɂ��ẮA�n���̎��Ԃ����n���̋@���S�ۂ��鎖���ӎ����Ď��g�܂��Ɨǂ��B�@�@
2.�č����ʁi���]�j
- ����@�\�a�@�̗l�X�ȗv���ɂ��Ă͌p�����ēK�ȑΉ����Ȃ���Ă����B
- IA���|�[�g�ł́A��������ڕW�l��B�����Ă���@���̓�������E���̈ӎ��̍����������������B
- ��Ö@�{�s�K������ь��J�Ȓʒm�ւ̓K���ɂ��āA�g�D�̐��ƐӔC�̖��m���ɂ��Ă��v�������Ă���B
- �@�߁A�K�C�h���C���̏���ɂ����Ă����Ȃ��A����@�\�a�@�̗v�������Ă���Ɣ��f����B
�i�w�E�����F����ɉ��P���]�܂�鎖�j
- �L�Q���ے����ψ���A���ጟ�����ψ���̕ɂ��ẮA���������Ĕ��h�~�������ǂ̂悤�Ƀ��j�^�����O���Ă��������ۑ�ł���B�d��ȈČ��̂��̌�ɂ��Ă̓K���g�`���[�g�ȂǂŊǗ�����邱�Ƃ��]�܂����B
- ���Ҍ�F�̑��ɒ������I�Ƀ��j�^�����O������Ƃ��āA����Ɋ֘A����L�Q���ۂ�A��p�v���Z�X�Ɋ֘A����L�Q���ۂȂǂ��l������B�����ɂ��āA�Ǘ��}����p���ĉi���I�Ƀ��j�^�����O���邱�Ƃ��]�܂����B
3.����̈�È��S�O���č��ψ���Ɍ�����
- ���S����Ɋւ��āA�N�Ԃ̑S���S���A���̂����d��Ȏ��̂̋^���ɂ��ً}�R���ΏۂƂȂ������S���A
����ɏd��Ȏ��̂Ɣ��f���꒲���ΏۂƂȂ������S���A�����̌��ʈ�Éߌ�ɂ�鎀�S�Ɣ��f���ꂽ��
�S���ɂ��āA�S�K�w�̃s���~�b�h�ŕ\�����W�v���ʂ�������ꂽ���B - ��ܕ��̋^�`�Ɖ��̃��A�N�V�������ɂ��ẮA������p�����ĕ��ꂽ���B
�ȏ�