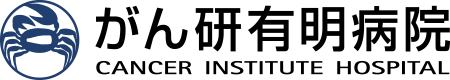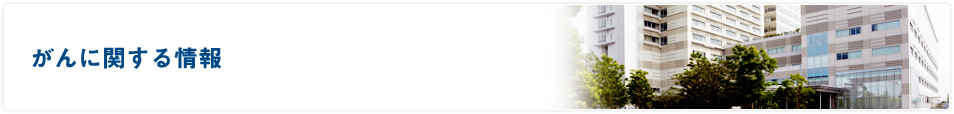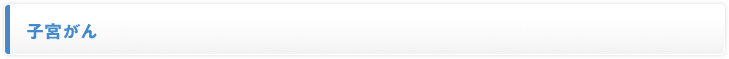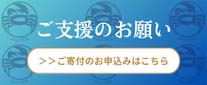- HOME
- ����Ɋւ�����
- ����̎�ނɂ���
- �q�{����
�q�{����
���L���a�@�̎q�{����f�Â̓���
���L���a�@ �w�l�Ȃł́A���w�Ö@������ː����Õ��ƘA�g���A���҂���̏ɉ������œK�Ȏ��Õ��j�����肷��W�w�I���Â���Ă��܂��B
�f�Â̓���
- �ʉ����ÁF���҂��Ƃ̂���̓����E�g�̓I�E���_�I�E��]�ɉ��������Â����{�B
- ���m�Ȑf�f�Ɋ�Â����ÁF�זE�f�E�g�D�f�����p���A�I�m�Ȑf�f�Ǝ��Õ��j������B
- ���Ì�̌��f�E�t�H���[�A�b�v�F�Ĕ��̑��������ɓw�߂�B
- QOL�i�����̎��j�̌���ɔz���F
- ������E���O���i���e頏Ǒ�j
- �����p����\�h�O���i�ނ��݁E������Q�̃P�A�j
�X�q�N���u�i�R������Âɔ����E�ё�j
�q�{����ɂ���
�q�{����Ƃ�
�q�{�͏����̍��Ւ����Ɉʒu���A���E�ɗ���������܂��B�q�{�́u�q�{�z���v�i�q�{�̏o���j�Ɓu�q�{�̕��v�i�q�{�̏㕔�j�ɕ�����Ă���A�����̕��ʂɔ������鈫����ᇂ��u�q�{����v�ƌĂт܂��B
�q�{����ɂ͑傫�������āu�q�{�z����v �� �u�q�{�̂���v������܂��B
- �q�{�z����: �q�{�z���ɔ������邪��ŁA��Ƀq�g�p�s���[�}�E�C���X�iHPV�j�̊����������Ƃ���Ă��܂��B����̎�ނɂ́u�G����炪��v�Ɓu�B����v������A���{�ł͑B����̊�������r�I�����X���ɂ���܂��B
- �q�{�̂���: �q�{�̕��i�q�{�����j�ɔ������邪��ŁA�قƂ�ǂ��u�B����v�ɕ��ނ���܂��B�z�������������ǂɊ֗^���A���ɕo�O��̏����ɑ����݂��܂��B
�q�{����̔��Ǘ��ƔN��z
2019�N�̃f�[�^�ł́A
- �q�{�z����̐V�K�늳�Ґ��� 11,283�l�A���S�Ґ��� 2,871�l
- �q�{�̂���̐V�K�늳�Ґ��� 17,880�l�A���S�Ґ��� 2,863�l �ƂȂ��Ă��܂��i2022�N���v�j�B
���� �q�{�z�����20�ォ��}�����A�D�P����]����Ⴂ����ɉe����^���邱�Ƃ��������Ă��܂��B����A�q�{�̂����50�`60��Ŕ��ǂ̃s�[�N���}���܂��B
�q�{����̌���
�q�{�z����̎�Ȍ�����HPV�����ł��BHPV�͐��s�ׂ���Ċ������A�����X�N�^HPV�i16�^�A18�^�A33�^�A52�^�A58�^�Ȃǁj������̔��ǂɊ֗^���܂��B�������A���������S�Ă̐l������ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��A�Ɖu�̓����ɂ���ăE�C���X���r������邱�Ƃ�����܂��B
�q�{�̂���̎�ȗv���̓z���������ł��B���ɃG�X�g���Q���i�����z�������j�̉e�����₷���A�����E���D�A�r����Q�A���X�E�������nj�Q�Ȃǂ����X�N���q�Ƃ���Ă��܂��B�q�{�̂���́u�G�X�g���Q���ˑ����iI�^�j�v�Ɓu��ˑ����iII�^�j�v�ɕ��ނ���AI�^�͔�r�I�\�オ�ǂ��Ƃ���Ă��܂��B
�f�f���@
����
�q�{����̐f�f�ɂ́A�ȉ��̕��@������܂��B
- �זE�f�����i���f�j
- �q�{�z����q�{�̕��̍זE���̎悵�A����זE�̗L���ׂ܂��B
- �q�{�z����̐f�f���͖�95%�ł����A�q�{�̂���̏ꍇ�͖�50%�ł��B
- �g�D�f�i�����j
- �q�{�z����q�{�����̈ꕔ���̎悵�A���ڂ����������s���܂��B
- �摜�f�f�iMRI�ECT�EPET�j
- ����̐i�s�x��]�ڂ̗L�����m�F���܂��B
- HPV����
- �q�{�z���ٌ̈`���i�O����a�ρj�����A�n�C���X�N�^HPV�̗L���ׂ܂��B
�����@
�q�{�z����
- �����i�K�iIA�EIB���j: �q�{������p�i�~���؏��p�E�L�Ďq�{�z���E�o�p�j�������ł��܂��B
- �i�s���iIB���ȍ~�j: �L�Ďq�{�S�E�p �� ���ː����Â��s���܂��B
- �V���ȍ~: ���ː��Ö@�Ɖ��w�Ö@�̕��p����ʓI�ł��B
�q�{�̂���
- ��{����: �q�{�S�E�p���W�����³��B
- �����ŔD�P����]����ꍇ: �z�������Ö@�ɂ��o�ߊώ@���\�ł��B
- �i�s���E�]�ڂ�����ꍇ: ���w�Ö@����ː��Ö@���s���܂��B
���{�b�g�x����p�E���o����p �ߔN�A��p�x�����{�b�g�u�_���B���`�v�ɂ���N�P��p�������Ă��܂��B�����������A�p��̉��������Ƃ������b�g�ł����A�K���ɂ͐T�d�Ȕ��f���K�v�ł��B
�\�h��
- HPV���N�`���̐ڎ�
- 9�����N�`���i�V���K�[�h9�j��90%�̗\�h���ʂ������܂��B
- ���{�ł͏��w6�N���`���Z1�N���̏��q��Ώۂɒ���ڎ킪�s���Ă��܂��B
- ����I�Ȃ��f
- 20�Έȏ�̏�����2�N��1��̎q�{�z���f�𐄏��B
- �o��̏����͎q�{�̂���̌��f���l���B
�܂Ƃ�
�q�{����͑��������E�K�Ȏ��Âŏ\���ɑΏ��\�ł��B���� HPV���N�`���̐ڎ�����I�Ȍ��f���邱�Ƃŗ\�h�E�����������\�ɂȂ�܂��B���s���ȓ_������A���L���a�@�̂��k�����܂ł��C�y�ɂ����k���������B