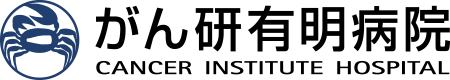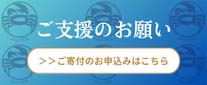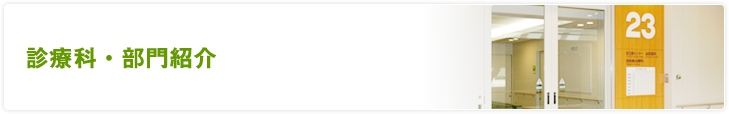
看護師特定行為研修
新着情報|特定行為研修について|修了者の声|募集要項|Q&A|問い合わせ先
修了者の声
-
 看護部 10階東病棟
看護部 10階東病棟
Oさん修了区分/修了年: 栄養に係るカテーテル管理関連・創部ドレーン管理関連(2024年)
1.特定行為看護師を目指したきっかけ
特定行為看護師を目指そうと思ったのはタイムリーに医療提供を行うことができると考えたためです。看護師になり経験を重ねるなかで、実際の場面ではアセスメントにつなげることはできても手技を行うことはできず、医師へ依頼し対応を待つ場面が多くありました。そういった場面を打開できるようなものはないかなと探し始めたのがきっかけです。2. 特定行為研修はどうだったか
研修のe-ラーニングは幅広い領域で量が多く大変でしたが、自分のペースで聴講でき、解らなければ何度も繰り返し聴くことができ、学びを深めることができました。医師がどのように考え、判断するかを学ぶプロセスはとても新鮮でした。それと同時に学ぶべきことの深さと多さに驚き、研修を終えた今でも自分をアップデートさせる重要性や必要性を強く感じています。3.特定行為看護師としての意気込み
主に術後ドレーンの抜去や末梢挿入型中心静脈カテーテル(PICC)挿入の実践的なことや、患者さんの状態を把握・アセスメントして医師に治療方針の確認や相談をし、看護師と医師の調整をしています。まだ特定行為看護師として働き始めたばかりなので出来ることは少ないですが、どんどん挑戦して活動の幅を広げていきたいと思っています。 -
 看護部 ICU
看護部 ICU
Kさん修了区分/修了年: 呼吸器(気道確保に係るもの)関連・呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連・循環器関連・栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連・動脈血液ガス分析関連・循環動態に係る薬剤投与関連(2025年)
1. 特定行為看護師を目指したきっかけ
患者さんの個別的なニーズに応え、より質の高い看護を提供したいと考えました。また、医療チームの一員としての役割を果たすために、看護の視点だけでなく、医学的な視点を学ぶことができる特定行為受講を決めました。2. 特定行為研修はどうだったか
特定行為に関連した知識だけでなく、医療安全や意思決定のプロセスなどを学ぶことで看護実践を客観的に振り返ることができました。受講中は大変でしたが、同じ志を持つ受講生と切磋琢磨することができた貴重な機会でした。3. 特定行為看護師としての意気込み
チーム医療に貢献し、患者さんにとって最適な治療を追求して行きます。特定行為を通じて、多職種連携を強化することで、より質の高いケアを提供したいと考えています。院内の急性期ケアや急変対応、患者の重症化予防ケアの質の向上に貢献したいと思います。 -
 看護部 11階東病棟
看護部 11階東病棟
Kさん修了区分/修了年: 栄養に係るカテーテル管理関連・ 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 (2024年)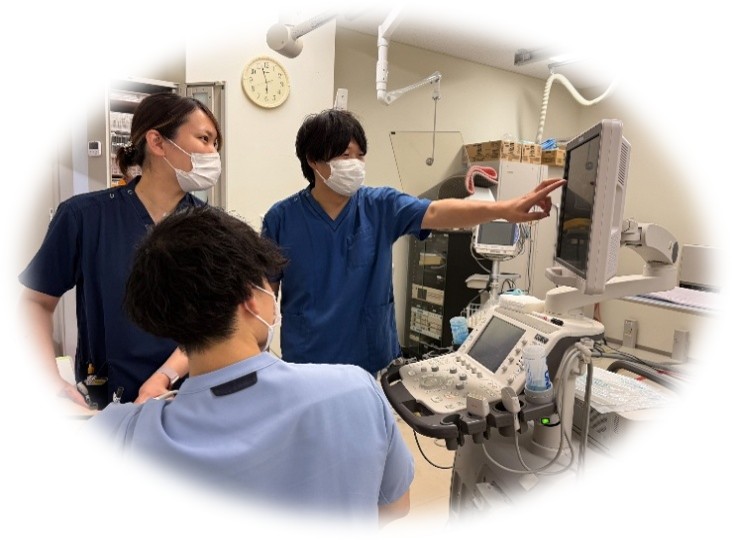
1. 特定行為看護師を目指したきっかけ
看護師特定行為研修は師長にきっかけをいただき、知りました。知識を深めるだけでなく、手技を実践することで専門性を高め、看護の幅を広げる大きな一歩になると考えました。より質の高い看護を実践するために受講を決意しました。2. 特定行為研修はどうだったか
通常勤務と学習時間の両立に苦労し、モチベーションを保つことも容易ではありませんでした。身近に経験者が少なく、不安を感じることもありましたが、周囲のサポートもいただきながら自らを律して時間を捻出して研修を修了できたことは大きな自信になりました。3. 特定行為看護師としての意気込み
特定行為研修修了者として、医学と看護の知識を統合し、患者さんに最適なケアを提案できるよう努めていくと同時に、自己研鑽を続けて知識と技術を維持・向上させていきたいです。また、同じ道を歩む仲間を増やし、研修を経験した立場から支え合える環境づくりにも貢献していきたいです。 -
 看護部 教育担当
看護部 教育担当
Hさん修了区分/修了年: 栄養に係るカテーテル管理関連・動脈血液ガス分析関連(2024年)
1. 特定行為看護師を目指したきっかけ
特定行為看護師が人工呼吸器装着中の患者さんの離床支援を行っていると知り、特定行為看護師の役割を知りました。患者さんに何か異変が起きたときなどに、医師がすぐに対応できず到着を待つ間に何もできないもどかしさを感じていました。その経験から迅速な対応ができるようになりたいと思い、特定行為看護師を目指しました。2. 特定行為研修はどうだったか
仕事と勉強の両立は決して簡単ではありませんでした。職場の協力と同じ志を持つ研修生とのつながりに支えられ、最後までやり遂げることができました。互いに励まし、協力しながら学びを深めることができたことは、良い経験になりました。3. 特定行為看護師としての意気込み
患者さん一人ひとりの個別性を尊重し、様々な視点から状況を捉えることで必要なケアを最適なタイミングで届けられるよう、チーム医療のキーパーソンとして多職種と連携しながら取り組んでいきたいです。研修にも関わることとなり、研修生が安心して学び、成長できる環境づくりに力を注ぎながら、実践的なサポートも行っていきたいです。